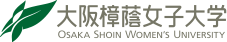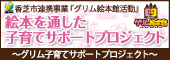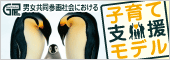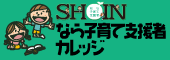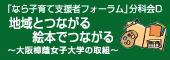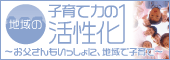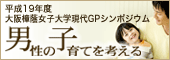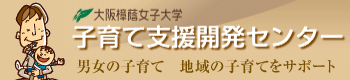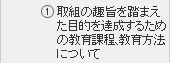 |
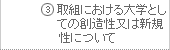 |
| TOP > 文部科学省選定 大学教育改革支援プログラム > 学生による地域協創型子育てモデルの開発 > 取組について > 取組の実施体制 |
 |
取組について |
取組の実施体制 |
|
| 本取組での目的を達成するための教育プログラムは、3つの課程から構成されます。 | |
I .必要な「学問的基礎」を涵養するための講義(「基礎力」の養成) |
|
| 主として全学共通の教養教育科目に、1年次と2年次の学生を対象として、基礎科目群(「女性学・女性史」「ボランティア活動論」等)を配置し、男女共同参画の理念と子育て支援に必要な基礎を学びます。また、発展科目群(「児童福祉学」「家族関係論」「子育てとコミュニティー」等)を2年次から4年次の学生を対象に設置します。 これらの科目により、学問的知識について継続、発展的な教育を行い「基礎力」を養います。 |
|
II .行政による施策および企業の就労環境の比較・検討・評価と対案作りを通じて地域・社会での子育て支援策を理解するための演習(「相談力」「情報力」の養成) |
|
| 「基礎演習」および「教養ゼミナール」の演習において、教育学、福祉学、女性学、社会学等を専門とする教員の指導の下、香芝市や東大阪市など地域の子育て支援の現場と企業における育児休業・休暇や子ども看護休暇等の状況について理解します。 また、複数の自治体や企業による子育て支援事業の比較・検討・評価を行い、地域で実施可能な子育て支援施策案作りを学生自ら行います。 演習授業により、地域の子育て支援の現実を学び、男女共同参画社会おける子育て支援について理解を促し、「相談力」「情報力」を養います。これらの成果を、子育て支援開発センターに報告し、次年度の I 、II の取組にフィードバックします。 |
|
III .学生による地域での具体的な「子育て支援プロジェクトの企画、立案、実施」を行う演習 |
|
| 3年次から4年次の学生を対象とした「演習」で、地域の実情に合わせたプロジェクトを学生が主体となり企画・立案し、地域で実施します。父親参加を促す教室やイベント等のプロジェクトを公民館や保育所・幼稚園など地域で開催します。 学生は自ら考えたプロジェクトを遂行することで「コーディネート力」「実践力」を涵養し、自己有能感を高めます。[図2参照] |
|
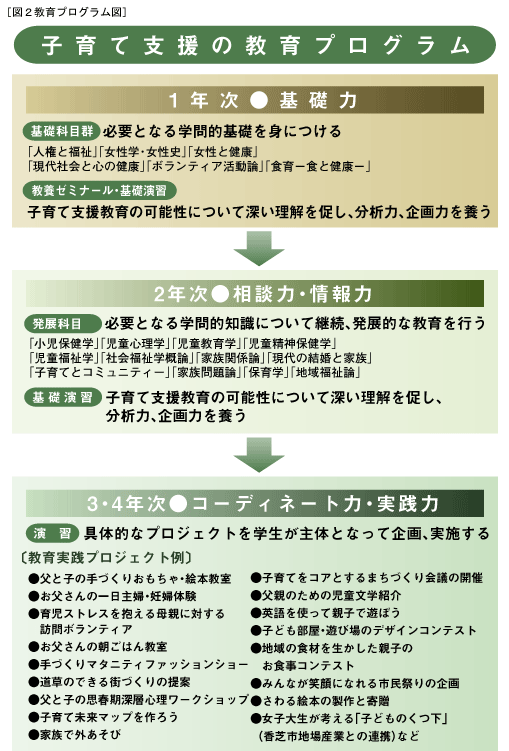 |
|
Copyright (C) SHOIN GAKUEN. All rights reserved.