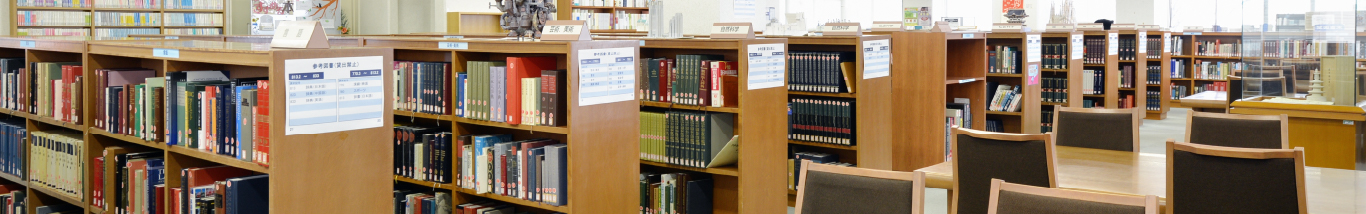
人間栄養学専攻概要
栄養・医療・食品に関する高度な知識と実践力を兼ね備えた「食と健康」のプロを育成します。
食と健康を多角的に見つめながら、人間の存在そのものを学際的に追究します
過剰栄養や栄養不均衡による生活習慣病、食物により媒介される感染症、遺伝子組み換え食品の社会的認知、さらにはストレスによる過食・拒食やダイエットによる栄養欠乏、入院患者および高齢者の低栄養状態・・・・・・。
現代社会では、従来の学問の枠組みでは解決が難しい問題が多発し、消費者が「食」に不安や不信感を感じる生活を余儀なくされています。こうした状況を背景にわが国では、栄養学的な側面にとどまらない幅広い視野をもったプロの育成が大きな課題となっています。
「人間栄養学」という学問では、人体の構造や生理機能といった身体的側面だけでなく、心理面、精神面、食行動や生活スタイルの変化など、私たちを取り巻く社会環境を含めた人間の総合理解をベースに、「食」と「健康」のあり方、つまりは人間の存在そのものを学際的に追究します。
高度な専門性を体系的に身につける独自のカリキュラム
食物科学と医学・保健学を融合し、学部教育との継続性を重視した体系的・系統的なカリキュラムを編成。
食物科学と医学・保健学を有機的に融合させた独自のカリキュラムを編成。学部教育との継続性を重視し、4年間で培われた専門性を系統的に向上させる目的で、教育課程群を「研究基礎科目」「研究展開科目」「研究実習科目」「研究演習科目(修士論文・課題研究指導)」の4科目で構成します。さらに、修了後の進路から2つの履修モデルを設定し、実践的な知識・技能を効果的に身につけられるよう配慮しています。
画像はクリックで拡大できます。
※掲載している情報は、2025年度現在のものです。
学びを支える制度
●奨学金制度
本大学院には、独自の公募制・推薦制の奨学金制度があります。公募制の「給付奨学金」は、1、2年生の大学院が対象で、経済的事情により就学が困難と認められた学生に給付されます。また、推薦制の「特別給付奨学金」は、2年生が対象で、専攻長の推薦を受けられた方に給付されます。どちらもその年度に納入すべき授業料の半額相当額で、返還不要となっています。
●長期履修制度
諸事情により本学修士課程における教育・研究に専念することのできない方は、就業年限を3年または4年に延長ができ、尚且つ学費総額は増えない制度があります。
詳しくは、募集要項をご参照下さい。
●昼夜開講制度
社会人が働きながら無理なく通学できることを最優先に考え、授業時間帯を平日の夕方以降や土曜日の昼間を中心に配置しています。一部の科目については土日や長期休暇期間などを利用した集中講義形式で授業を展開します。
※本専攻では、6講時:18:20~19:50を中心に授業を開講します。一部科目は、7講時:20:00~21:30またはオンデマンド開講。土曜日は昼間開講となります。
★オンラインを活用した遠隔指導も適宜取り入れます。
確かな資格をもとに広がる多彩な修了後の進路
臨床栄養師
臨床の現場に特化した資格といえるのが、「臨床栄養師」です。
近年、NST(栄養サポートチーム)が組織され医療が行われており、より高度な臨床栄養の知識、技術およびマネジメント能力を有する臨床栄養師は、不可欠な存在となっています。
本専攻では、複数の臨床栄養師および研修生を輩出しており、現在、総合病院等でNSTの一員として活躍しています。

- 臨床栄養師資格
「臨床栄養師」資格は、人間栄養学に基づいた臨床栄養の知識、技術およびマネジメント能力を習得し、栄養ケア・マネジメントの質の向上に貢献できる能力を持つ者の育成のため、日本健康・栄養システム学会の主導で設立されました。資格取得には100時間の認定講座と900時間の臨床研修を受け、その後、認定試験と論文試験に合格することが必要です。
- 日本で最初の認定講座指定校
本大学院は、日本で初めて設立した「臨床栄養師認定講座」指定校で、資格取得に必要な100時間の認定講座は、本大学院で在学中に受講可能です。また900時間の臨床研修は、本大学院の開講科目「人間栄養実践研究」での病院研修に参加すれば在学中に修了でき、「臨床栄養師」認定試験の受験資格を取得することが可能となります。
栄養教諭
- 栄養教諭の「専修免許」が取得できる数少ない大学院

栄養教諭とは、教育現場で、学校給食の管理とともに、児童・生徒が正しい食習慣を身につけるための食教育を教員・家庭・地域などと協力して行う専門職です。
この栄養教諭の免許には、「専修免許状」「一種免許状」「二種免許状」の3種があり、本大学院では、栄養教諭一種免許状を有している人を対象として、「専修免許状」が取得できる課程を設置しています(総修得単位数44単位以上が必要)。また、一種免許状を有しない人についても、本学健康栄養学科で開設している科目を履修すれば、専修免許状を取得できる場合があります(同時に管理栄養士を有していること)。
栄養と食品のプロ
本大学院の「人間栄養実践研究(研究実習科目)」では、食品成分の有効性評価に必要な知識や技術習得だけでなく、食品開発や食品管理分野で必要とされるスキルも修得します。また、臨床研究の実施法やデータ解析の知識と技術は、臨床や公衆衛生の場における栄養食事指導や研究活動に幅広く応用が可能。課題発見能力、問題解決能力、研究遂行能力を身に付け、各分野でのオピニオンリーダーをめざします。
実践力を高める「人間栄養実践研究」
医療機関、スポーツチーム、食品関連企業における4週間の臨地実習により、実践力を高めます。
研究基礎・展開科目で培った専門的な知識・技能を実践的に高めるため、「人間栄養実践研究(研究実習科目)」として臨地実習を導入。実習先担当者および本大学院研究指導教員による綿密な指導のもと、修了後の進路や研究内容に応じた実習先において学びを深めます。
医療機関での臨地実習
医療機関での臨地実習では、「栄養・食品のプロ」としての管理栄養士の特性を基礎として生かしながら、実際の臨床の現場で行われている「栄養管理」や「栄養食事指導」に重点を置いて学びます。具体的には、栄養管理プロセス(アセスメント、栄養診断、モニタリングなど)の施行とその評価、さらには、これらの一連の作業内容と結果を集積・分析し、創意工夫・研究できる力を養成します。

食品関連企業での臨地実習
今日、食品には単にエネルギー補給という目的だけでなく、疾病の一次予防の観点からその食品の持つ機能性が注目されるなど、さまざまな要素が求められるようになりました。食品関連企業では多様化する消費者のニーズに応えるべく、生化学・バイオテクノロジーなどの技術を駆使し、基礎研究から商品開発、そして商品の品質管理やフォローまで行っています。食品関連企業の臨地実習では、最前線の企業研究室において実験や業務助手を体験することにより、食品企業等を研究できる力を養成します。

スポーツチームでの臨地実習
「より速く、より高く、より強く−共に(オリンピック憲章 第1章 規則10)」。スポーツ選手のパフォーマンス向上には、トレーニングだけではなく、食・栄養が重要な役割を担います。スポーツ選手を食・栄養面からサポートする専門職が公認スポーツ栄養士です。スポーツ選手の栄養管理を実践している公認スポーツ栄養士の元で実習を実施します。実習を通じて、スポーツ現場における科学的根拠の利用についての現状と課題を学びます。


社会医療法人近森会 近森病院との包括提携(チーム医療の実践に向けて)
近森病院(高知市)と大阪樟蔭女子大学は、2009年4月に医療・臨床栄養における知的・人的資源の交流提携を推進し、相互の教育と研究や地域社会への貢献を目的として包括提携に関する協定を結びました。※1
これは「臨床栄養師」認定講座指定校である本学と、栄養サポートチーム(NST)の先進的な取り組みで全国的に有名な近森病院がお互いに連携して活動していくことに合意したものです。
※1)朝日新聞2009年9月11日に記事掲載
くすのき健康栄養センター
(正式名称:大阪樟蔭女子大学 大学院 人間科学研究科 人間栄養学専攻附属 くすのき健康栄養センター)
地域社会の健康維持・増進を栄養面からサポート
本大学院附属「くすのき健康栄養センター」では、栄養の専門家の教育・育成に関するアカデミックなスキルを一般に提供するとともに、地域の方々が心身ともに健康であり続けられるように支援しています。
具体的には当センターを、地域連携と教育活動の拠点として活用し、一般の方を対象に健康相談や食育相談、料理教室や健康的な食べ方セミナーなどを開催していきます。また、大学院生の教育ならびにすでに社会人で活躍している専門家の再教育に取り組んでいます。さらに、このような活動を通じて、東大阪市を中心とする近隣地域の行政機関、医療関連団体、栄養関連団体、企業並びに近隣大学等との連携をはかり、地域での包括的な栄養と健康増進関連の社会貢献に努めます。




