
くすのき地域協創センター

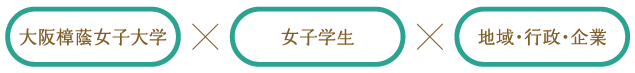
くすのき地域協創センターは、教育・研究・地域連携の3テーマを柱にし、地域との連携による学生の実践活動を進めることで、互いを高めていくサイクルを形成し、具体的な地域課題の解決を図っていきます。
イキ×ラボ・チャレンジプロジェクト
大阪樟蔭女子大学では、学生が自主的に行う課外活動や資質向上のための研修・研鑚の活動に対し、資金やサービスを提供し、その継続的な運営を大学が支援する『いきいき★キャンパスライフ・プロジェクト』という取り組みを2007年から行ってきました。
2015年からは、新しく「くすのき地域協創センター(愛称:イキ×ラボ)」が設置され、地域志向に特化した『イキ×ラボ・チャレンジプロジェクト』として継続しています。
本プロジェクトは、地域社会の中で活躍できる女性の育成を目的に、授業やサークル以外で、学生が大学での学びや自分たちの力を活かし、主体的に地域の課題解決などに取り組む活動に対して、大学が支援を行う制度です。学生の皆さんには、このプロジェクトでの活動をとおして、主体的に物事に取り組む社会的・創造的な力を身に付けていただきたいと考えています。
「くすのき地域協創センター(愛称:イキ×ラボ)」は、採択されたプロジェクト活動団体に対して、①活動資金の提供 ②計画・運営面でのアドバイス、といった形で学生の活動をサポートしていきます。
2021年度より『イキ×ラボチャレンジプロジェクト』は
SDGsとリンクし、より社会の課題解決に一層つながるようになっています。

L型
| プロジェクト名 | 活動概要 |
|---|---|
| グリムプロジェクト2023 | 東大阪市・香芝市・門真市・和歌山県かつらぎ町など自治体と連携し、親子に絵本の読み聞かせを行い、絵本の魅力を感じてもらい、親子で絵本を読むことを習慣づけてもらうこと、そして地域の方々と交流し、地域の課題(子育て支援や読書推進)に貢献することを目的とする。また、絵本だけでなく製作活動やダンス等を行い、親子ともに充実感を味わい、人の温かさや地域の人と人との関わりを感じることができるような空間をつくっていく。 |
| Re:Shoinきずなとれいる |
地域包括支援センターヴェルディ八戸ノ里、永和校区福祉委員会、東大阪市社会福祉協議会と連携し、地域在住高齢者を対象とした3つのイベントを実施する。イベントは、夏の大運動会・旅行へ行こう!・夏祭り・の3つを実施予定。地域在住高齢者の健康の維持・増進を目指し、健康栄養学科の臨床栄養学の学びを活かしながら行いたいと考えている。 |
| キャンドルナイト | 西梅田の100万人のキャンドルナイト(12月)と、門真市七夕キャンドルナイトの夕べ(7月開催)に参加。それぞれのイベントごとに違った作品を出展し、大阪の街の活性化、エコについて来場者に考えてもらう機会を提供することを目的とする。SDGs17ターゲットの中のエネルギー問題をつなげ、不要になった化粧品をキャンドルの着色料をとして使用し、エコキャンドル作りを実際に体験など、新しい取り組みにも挑戦。参加者にリサイクルについて考えてもらう機会を提供する予定。 |
|
髪の毛で夢をつなぐ |
小児がんや先天性の脱毛症、不慮の事故などで頭髪を失った子どものために、寄付された髪の毛でウィッグを作り、無償で提供するヘアドネーションの活動に賛同し、通常、ヘアドネーションカットは美容室で行い料金発生するところ、本プロジェクトでは、本学の美容コースの学生が無償で行う。活動は、本学の学生及び、教職員を対象に実施予定。また、昨年度に開催した座談会での学びを発展させ、オープンキャンパスにてウィッグの着用体験の企画中。 |
|
メイクラボ |
近年、安価な化粧品が流通するようになり手軽にメイクを楽しめるようになった一方で、化粧の低年齢化や化粧品の大量廃棄といった新たな問題も生じていいる。そこで、これらの問題の解決に向けて化粧ファッション学科での学びを活かしたセミナーやイベントを学生の視点から企画・実施し、化粧を安心安全に楽しんでもらう提案を行うと同時に、化粧にまつわる諸問題について意識を高めてもらう機会を提供を考えている。ラッシュジャパン合同会社様、イコーラム様と連携し,SDGsについて学ぶイベントを実施予定。 |
S型
| プロジェクト名 | 活動概要 |
|---|---|
| ecoプロジェクト |
昨今、問題視されている「プラスチック問題」の解決に向けて、「自分たちができる範囲で、身近なことから取り組む」を目標に、ペットボトルキャップと使い捨てコンタクトケースの回収を学内と附属幼稚園に設置。毎回、多くの方が協力してくださっており、昨年はアイシティ様から感謝状もいただきました。今年度は、回収活動だけでなく、環境問題の現状について少しでも多くの方に知っていただけるよう、また、社会や環境をより良くするには1人ひとりの協力が必要であることを広める活動を目的に活動予定。 |
| KSK10 | 東大阪市危機管理室と連携し、花園北校区自治会を対象にしたイベントを1回、親子を対象にしたイベントを1回の計2回実施予定。1回目のイベントは、小学校の避難訓練に協力されている東大阪市の花園北校区の自治会を対象に、アレルギーについての基礎知識や、アレルギー対応をするということはどういうことなのかについてクッキングを通して学んでもらうイベントを実施予定。2回目のイベントは、その避難訓練の際に小学生にチラシを配布いただき、小学生とその保護者を対象に行います。食べたものを実際に調理しながらアレルギーと災害について考えることで、より興味を持ってもらい、アレルギーについての理解を深めることに繋げることができるのではないかと考える。 さらに、SDGsやフェアトレードを紹介することで、同じ時代を生きる世界の人々の生活背景を見る力を養えように、少しでも興味を持ってもらう。 |
| ニシンを食べよう! 缶詰ラボ |
ニシンが、近年、国内の漁獲量が回復してきているにも関わらず、消費が伸び悩んでいる現状。そのような中、持続可能な水産業と魚食文化には、国内漁業を支える消費が不可欠な状況となっているため、国内漁業の現状についてさらに学びつつ、日本の水産業に不可欠な沿岸漁業資源の持続可能な有効利用を企業とともに考え行動に移したいと考える。主に、試作と試食を含めたレシピ開発(学内実施)、プレス発表会(メディア対象)、マルハニチロ北日本社HPでのレシピ公開(一般対象)の3つを実施予定。 |
| Possibilities of cosmetics ~化粧品の可能性~ |
食糧廃棄や衣服廃棄が問題となっている近年、毎年膨大な量のコスメも捨てられているという現状に向き合おうと思い、使用しなくなったコスメを捨てずに何か再利用できるのではないかと考えた。 |
その他の活動
1.松田先生ゼミ

企業との連携によるプロジェクト
フルーツを使ったおみやげ創作プロジェクト【大谷食品株式会社(かつらぎ町)】
和歌山県かつらぎ町産業観光課及び大谷食品と本学学生が連携し「かつらぎ町の新しいお土産を創作する」ことを目的に活動しました。計4チームの提案したお土産が正式に商品化され、販売イベント等を行いました。
大相撲香芝場所に係る商品開発プロジェクト【株式会社 C's(香芝市)】
大相撲秋巡業「香芝場所」に合わせて女子大生の視点から相撲場所の記念品を提案・開発しました。
靴下デザインプロジェクト【杉山ニット工業(香芝市)】
地場産業を活かした実用性のある靴下を、女子大生の視点で、デザインからマーケティング戦略まで提案し、商品化を目指すプロジェクトです。
学部(学科)によるプロジェクト
ヤングアメリカンズ【心理学科】
ヤングアメリカンズは、子どもたち自身の可能性の気づきを主としており、心理学科の学びと重なることから、教育プログラムの一環としています。自分自身の体験とともに、子どもたちの観察を通し、学びに繋げます。


行政・地域との連携によるプロジェクト
SPro地域福祉計画策定プロジェクト
【テーマ】 地域福祉計画(香芝市・社会福祉課)
香芝市の地域福祉計画を学生視点で考える
SPro(スチュデント・プロポーザー)を結成。
学生が参画し協働できる事業提案を行いました。

バリアフリー基本構想策定プロジェクト
【テーマ】 バリアフリー構想(香芝市・企画政策課)
香芝市と本学との「客観的根拠に基づく政策研会(EPRミーティング)」が
始まり、研究チームを発足。
「バリアフリー基本構想策定」を研究テーマに、市民アンケート調査の
設問及び集計結果に基づく統計分析を行い、香芝市バリアフリー
基本構想策定協議会に提出する報告書を作成しました。

